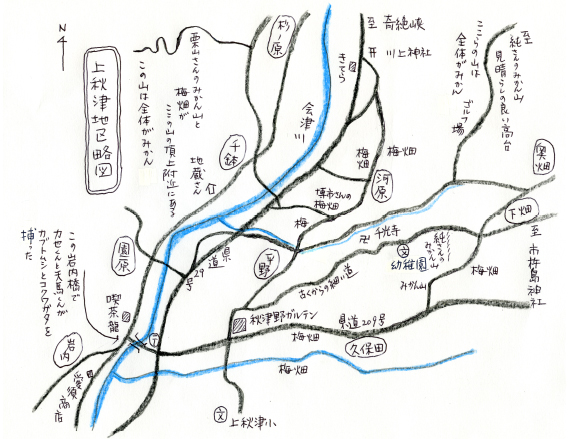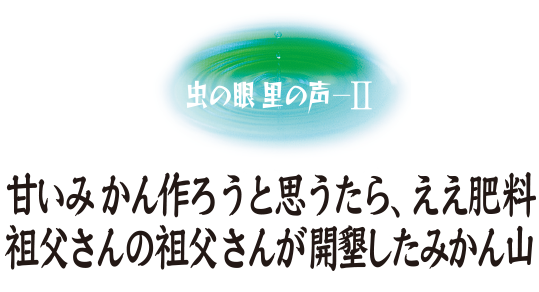
この日の午後から、段々畑で三宝柑を収穫していた山本純さんを、もう一度訪ねた。すでに谷底に近い段まで収穫作業は進んでいる。純さんが作っている柑橘類は、キンカン、三宝柑、極早生温州みかん、清見オレンジの4種類だ。
「みかんは安価であかんな。甘いみかん作らなあかんな。酸っぱいみかんは売れん。そんな時代や。甘いみかん作ろうと思うたら、肥料はええのをやらな、配合肥料。どんな品種がええと言うて植えても、皆が植えて、もう遅い時があらい。梅もやるよ。小梅は5月、南高梅は6月に収穫。梅は人手頼んでやらないかんから、梅一本でしよったら大変やよ。みかんは人にあげてもええしよ」
純さんの仕事はゆっくりと進む。モノラックのレールの上に腰掛け、出荷前の極早生温州みかんをいただく。
「ここは風が来んで温(ぬく)いんや、一番ええ。今年のみかんは、まあまあの値段やったと思うよ。甘いみかんにしよと思うたら、マルチにして雨が土に入らんようにせないかんのやけど、熱心な人はしよるで。農業しよるんが一番気楽なんかな。みかん作りしよって、ストレスいうんはないな。ここは、先祖から引き継いだみかん山。昔からあったんや。お祖父さんのお祖父さんの人が開墾したんやと思うけどな。この谷を全部埋めて平地にして、それを皆で分けよ、いう話もあったけど、結局、反対する人があって止まったけど。この山にあるみかんの樹は、100本くらい違うん」
「昔は、集落で遠足があってな、白浜へ行ったりよ。今は、もうないよ。宴会があって、カラオケがなかった頃やから、手拍子で歌ってよ。替え歌みたいなのを歌ったよ。酒飲まんと歌は出てこん。今の楽しみ言うたら、磯釣りによう行くんや。竿の先見とったら、仕事のこと忘れろ。ストレスないようになるよ。ホンダワラいう餌が、波で採れんのや。餌がないようになってな、近ごろは行っとらん」
純さんのみかん山は、高尾山に近い東側の山の頂上にもある。そこの三宝柑をこれから収穫するというので、軽トラックに乗せてもらって一緒に行くことになった。曲がった細い山道を一気に登る。作業小屋からは、モノラックの荷台に乗って頂上へ向かった。みかんのトンネルを潜り抜けていく。用心しないと、枝にぶら下がったみかんが顔にぶつかってくる。みかん山の頂上からは、田辺市街地と田辺湾、それに集落の遠足で行ったという白浜の岬が見えた。
「日和りのええ日には、四国の山が、ここから見えるで」。純さんはちょっと誇らしげだ。「風が冷やっこい。向こうは雪やろ」と、大阪や京都のある北の方角を見やった。