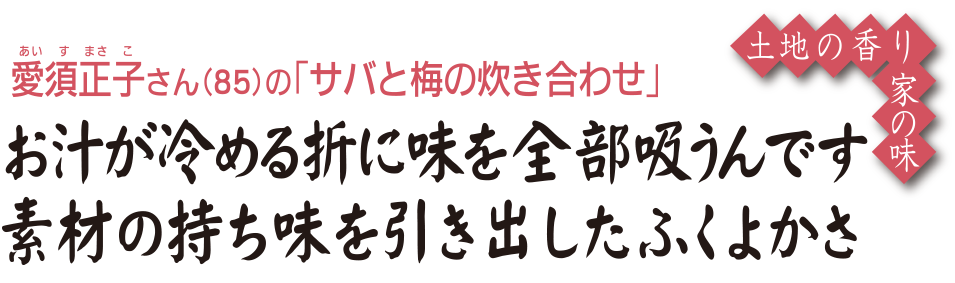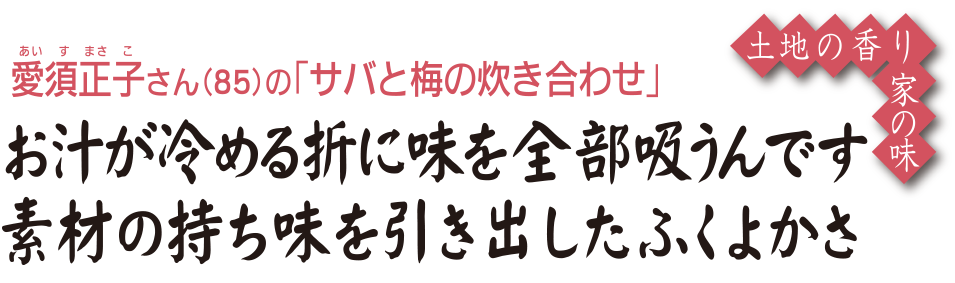牛乳パックを切り開いた上に、大きめのサバが輪切りにして置いてある。「魚や何かの折は、そのまますぐ放れるでしょ。まな板は日光消毒して置いてあるけど、使うのは牛乳パックばっかりね」と、正子さんは合理的な面を覗かせた。
「頭があったら大きかったですけど」と、サバの切り口を上にして鍋に並べていく。「お酒をちょっと入れてね。私は、どんな魚を炊いてもお酒をばね、底が見えないほど入れるんですよ」。一升瓶から日本酒をどぼどぼと、1センチほどの深さまで鍋に入れる。「水は、魚が浸かる程度にね。醤油も少し入れて、砂糖もね、ちょっと入れます。全部揃えてからね、炊きます。梅は、クエン酸が出てくるでしょ。だから梅は後で入れます。煮立ってからね」。
ここで点火し、強火で一気に炊きあげる感じだ。5分ほどで煮立ってきたら、サバの色が白く変わってきた。アクを取りながら、さらに炊き続ける。アクが出なくなった頃を見計らって、正子さんは鍋の真ん中に梅を「あまりぎょうさんはいらんやろと思うんですけど」と、5個入れた。
「こちらの人は、ちょっと酸いくらいのが好きなんです。ここらでは、サバを炊くと、必ず梅が入ります。お魚を炊く折、煮汁を沢山こしらえて炊くんです。魚を引き上げたら煮汁が残るでしょ。それで、煮汁を取って置いて、夏でしたら、梅ばかりをグツグツと、ほとんど汁が無いようになるまで炊くんですよ。そしたら、この梅がとっても美味しいんです。夏は、とにかく梅を沢山炊いてね。お膳の上に盛って置いときますと、ご飯の時には、これを取っていただきます。そうするとね、夏は汗をかくでしょ、その時の汗はあまり出ないしね。疲れがないんです。魚の煮汁に入れて炊く梅は、白梅なんですよ。味の付いてない梅。干しただけの梅」
梅を入れた後もグツグツと炊き続ける。小皿で煮汁の味を見た正子さん。
「ちょっと薄いような感じがしたんで、醤油をちょっと入れときますけど」と、醤油差しでくるりと鍋の回りに醤油を足した。「魚の色が変わるまで炊くから、25分くらいは炊くね」。煮汁が、最初の半分くらいまで減ってきたところで、火を止めた。
「鍋の中に、お汁あるでしょ。いい加減炊けたなあと思うたら火から下ろして、鍋を冷まします。魚でも何でも炊いた折は、お汁が冷める折に、味を全部吸うんです。何でもそうよ、どの料理でも。お汁に浸けとくとね、味がのるんです」
コンロから鍋を下ろして、鍋の蓋をしたまま、煮汁が熱くない程度まで冷めるのを待つ。
「正月は、イガミ(ブダイ)ちゅう魚があるんです。主人はね、七福神だったんです。男6人と女の子1人の兄弟。それが七福神言うんやで。そしたら女の子はね、弁天さん言うんや。兄弟が結婚したり、家を分かれたりしたでしょ。お正月には、皆、寄って来るんですよ。母屋へね。イガミちゅう魚は、海の魚やけどね、赤いきれいな鱗なんです。それを35センチくらいにね、大きさ揃えてね。そして、大きな釜でね、2級酒のお酒をば3本放り込んで、お水を入れて、お砂糖入れて、お醤油入れて、そして、その釜の中へ竹の皮を敷いてね、焦げ付かないように、魚がね。それで炊くんです。イガミちゅう魚をば、直径1メートル以上あるような大きな釜でね。そんな折、私はね、石を並べて、石の上へ釜を載せて、焚き口だけ開けといて炊いたんです」
「それを、50センチほどもある大きな皿があるんでね。大きな葉っぱを2枚敷いて、その上へ魚を一匹ずつ載せてね。それに青い松葉をちょっと添えるんですよ。素敵だで。それを一軒に一つずつ。冬ですからイガミが凍って、身が固うなって、美味しいんですよ。お汁が固まるからな」
隆盛を誇る梅問屋に、隣町のみなべ町から嫁に来て61年。多くの使用人をはじめ、人の出入りが多い旧家の女将として、家事を取り仕切ってきた正子さんには、気っぷと面倒見の良さが染み込んでいるようだ。
嫁に来た当時は、国鉄の駅まで梅を出荷するために馬を飼っていた。「私、ここへ来て間もなしにね、馬屋の中の敷き藁を出すのに、あんた一人で出すん気の毒やわ言うて、着物の裾をまくってね、女中さんを手伝いに行ったんやと。その頃の女中さんが言うんやけどな。何でも物珍しかったんと違うかね。私は、そんな人やったと」
昔話を聞かせてもらっているうちに、「サバと梅の炊き合わせ」は、ほどよく冷めたようだ。炊きたてのご飯と一緒にいただく。
「本当の素朴な味やからな。美味しいとも言えんし、美味しないとも言えん。何やら分からん。梅に消されて臭みもないしね」と正子さんが言うように、主張する味ではない。
素朴というのが、第一印象だ。味というよりは、素材の持ち味を引き出したふくよかさなのだ。醤油でも砂糖でもない、押しつけない控えめで深みのある味が、誰にでも好まれる「土地の香り」であり「家の味」そのものかも知れない。